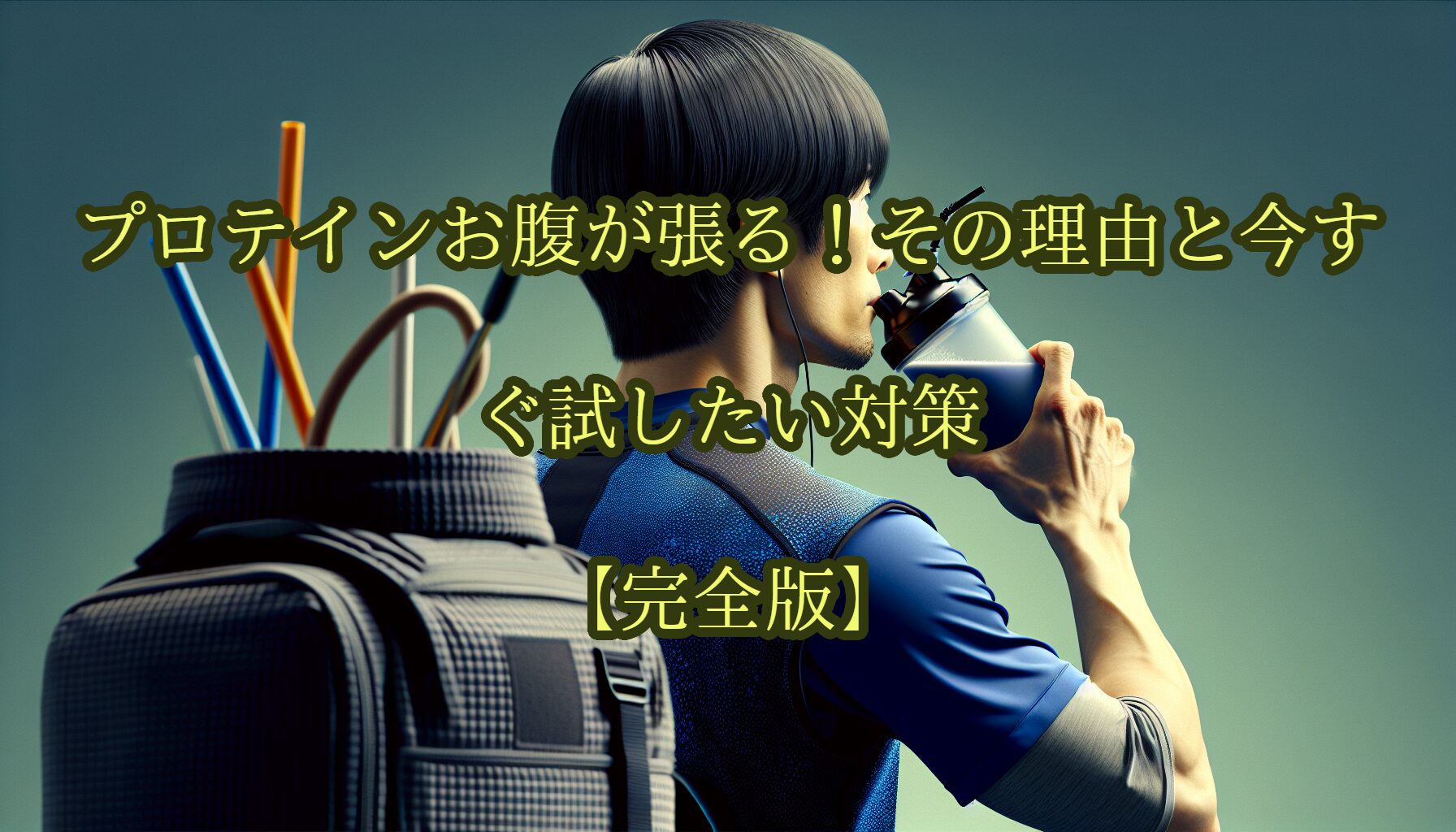健康やトレーニングのためにプロテインを飲み始めたのに、お腹が張って苦しいと感じる方もいるでしょう。
「せっかく頑張っているのにお腹が張って不快…」「このまま飲み続けても大丈夫かな…」と不安になりますよね。
しかし、お腹が張るからといって、プロテインを飲むのを諦めるのはまだ早いかもしれません。
原因を知り、ご自身に合った対策を試すことで、その不快な症状は改善できる可能性があります。
この記事では、プロテインを飲むとお腹の不快感に悩まされている方に向けて、
- プロテインでお腹が張ってしまう主な原因
- 今日からすぐに試せるお腹の張りを解消する対策
- 症状が出にくいプロテインの選び方のポイント
上記について、分かりやすく解説しています。
お腹の不快感を解消できれば、もっと前向きにトレーニングに取り組めるはずです。

プロテインでお腹が張る原因を解明

プロテインを飲んだ後にお腹が張ってしまうのは、決して珍しいことではありません。その主な原因として、プロテインの原料である牛乳に含まれる「乳糖」をうまく消化できない「乳糖不耐症」や、一度に多くのタンパク質を摂取したことによる消化不良が考えられます。せっかくトレーニングや健康のために飲んでいるのに、不快な症状に悩まされるのはつらいものです。
なぜなら、特に主流であるホエイプロテインは牛乳から作られており、製品によっては乳糖が多く含まれているからです。日本人の約3人に2人は、この乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)の働きが弱い、あるいは加齢とともに弱くなると言われています。そのため、体内で乳糖が分解されずに腸内でガスを発生させ、お腹の張りやゴロゴロ感といった不快な症状を引き起こしてしまうのです。
具体的には、比較的安価なホエイプロテインコンセントレート(WPC)は乳糖の含有量が多めです。また、一部の製品に使われている人工甘味料が腸内環境に影響を与えたり、シェイカーで混ぜる際に空気をたくさん飲み込んでしまうことも、お腹の張りに繋がるケースがあります。

乳糖不耐症が引き起こす症状
プロテイン摂取後にお腹が張る場合、乳糖不耐症が原因かもしれません。これは、牛乳や乳製品に含まれる乳糖(ラクトース)を分解する酵素「ラクターゼ」が体内で不足しているために起こる体質で、日本人では約3人に2人が該当するといわれているのです。
特にホエイプロテインには乳糖が多く含まれるため、乳糖不耐症の方が摂取すると、30分から2時間程度で様々な症状が現れることがあります。代表的な症状として、お腹の張り(膨満感)やゴロゴロという音(腹鳴)、ガスが溜まる不快感が挙げられます。
人によっては、腹痛や下痢といった、よりつらい症状を引き起こすことも少なくありません。もしプロテインを飲むたびにこうした症状に心当たりがあるなら、ご自身の体質が関係している可能性を考えてみましょう。
人工甘味料の影響
プロテインの飲みやすさを高めるために配合されている人工甘味料が、お腹の張りを引き起こす一因となる場合があります。アスパルテームやアセスルファムK、スクラロースといった成分は、体内で消化・吸収されにくい性質を持っているのです。
小腸で吸収されずに大腸まで到達した人工甘味料は、腸内細菌のエサとなり分解される過程でガスを発生させます。このガスが、お腹のゴロゴロ感や不快な膨満感の原因になる仕組みでしょう。
特に、一度に多くの量を摂取した場合や、特定の人工甘味料に対して体が敏感に反応する方もいるようです。もし心当たりがあるなら、人工甘味料を使用していないプレーンタイプの製品や、ステビアなどの天然甘味料を使ったプロテインに切り替えてみるのも一つの有効な対策となります。
冷たい飲み物との組み合わせ
トレーニング後に飲むプロテインを、冷蔵庫で冷やした5℃程度の水や牛乳で割る習慣は、お腹の張りを引き起こす原因になり得ます。冷たい液体が胃に流れ込むと、内臓の温度が急激に低下し、タンパク質を分解する消化酵素の働きを鈍らせてしまうのです。
特に胃腸がデリケートな方は消化不良を起こしやすく、腸内で異常発酵したガスが腹部膨満感につながるケースも少なくありません。さらに、内臓が冷えると血行が悪化し、腸の蠕動運動が低下することも一因でしょう。
この不快な症状を避けるには、プロテインを常温の水や人肌に近い30~40℃程度のぬるま湯で溶かすのがおすすめです。胃腸への負担が格段に軽くなり、タンパク質の消化吸収がスムーズになるため、お腹の張りを効果的に予防することが期待できます。
大豆由来の成分が合わない
ソイプロテインを摂取した際のお腹の張りは、大豆由来の成分がご自身の体質に合致していないサインかもしれません。大豆には「大豆オリゴ糖」や不溶性食物繊維が豊富に含まれています。これらは腸内で善玉菌のエサとなり発酵する過程でガスを発生させるため、腹部膨満感の直接的な原因となり得るのです。
特に大豆オリゴ糖は、適量であれば腸内環境を整えますが、一度に多く摂るとガスが溜まりやすくなるでしょう。また、大豆に含まれる「サポニン」という成分が消化管に影響を与え、不快感につながるケースも存在します。
もしソイプロテインが原因と思われる場合は、ホエイやカゼインといった動物性プロテインを試す価値があります。乳糖不耐症が心配なら、乳糖がほぼ除去されたWPI(ホエイプロテインアイソレート)や、えんどう豆を原料とするピープロテインを選択するのも有効な対策となります。
消化不良によるタンパク質の過剰摂取
タンパク質を一度に大量摂取すると、消化不良を起こしてお腹が張る原因となり得ます。私たちの体が1回の食事で効率よく吸収できるタンパク質量は、体重や運動量で個人差があるものの、おおよそ20g~40gが目安といえるでしょう。
この上限を超えるタンパク質は小腸で吸収しきれず、そのまま大腸へと送られてしまうのです。大腸に届いた未消化のタンパク質は、悪玉菌の格好のエサとなり、アンモニアなどの有害物質やガスを発生させます。
これが、お腹の張りやガスが溜まる不快感、気になるおならの臭いにつながるわけです。例えば、1食で30gのタンパク質が摂れるプロテインを飲む場合、直前の食事で鶏むね肉を100g(タンパク質約23g)食べていれば、過剰摂取になる可能性があります。
対策として、1回に飲むプロテインの量を半分にする、または食事との間隔を3時間以上あけるといった工夫を試してみてください。
お腹の張りを防ぐプロテインの選び方

プロテインを飲んだ後のお腹の張りは、製品の選び方を見直すことで改善できるかもしれません。お腹がゴロゴロする原因となりやすい成分を避け、あなたの体に合ったプロテインを選ぶことが最も効果的な対策と言えるでしょう。特に、牛乳でお腹の調子が悪くなりやすい方は、乳糖が少ない「WPI」や、植物由来の「ソイプロテイン」などを試すのがおすすめです。
その理由は、多くのプロテインの原料であるホエイ(乳清)に、お腹が張る原因となる「乳糖」が含まれているからです。日本人は体質的に乳糖を分解する力が弱い「乳糖不耐症」の方が多く、これがガスの発生やお腹の不快感につながってしまいます。また、製品によっては人工甘味料や添加物が多く含まれており、これらが消化の負担となっているケースも少なくありません。
具体的には、ホエイプロテインの中でも、特殊な製法で乳糖をほとんど取り除いた「WPI(ホエイプロテインアイソレート)」を選んでみましょう。もし乳製品自体が体に合わないと感じるなら、大豆由来の「ソイプロテイン」や、えんどう豆が原料の「ピープロテイン」といった植物性の製品に切り替えるのも一つの手です。

乳糖フリーのプロテインを選ぶ
プロテインを飲んだ後にお腹が張る場合、その原因は乳糖不耐症かもしれません。日本人は牛乳に含まれる乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)の活性が低い体質の人が多い傾向にあります。市販のホエイプロテインで主流のWPC(ホエイプロテインコンセントレート)は、乳糖が多く残っているため、お腹の不快感を引き起こすことがあるのです。
この対策として、乳糖を限りなく除去したプロテインを選ぶのが有効な手段となるでしょう。具体的には、WPI(ホエイプロテインアイソレート)という種類を選んでみませんか。WPIは特殊な製法で乳糖や脂質が取り除かれており、たんぱく質含有率も90%以上と非常に高いのが特徴です。
価格はWPCより少し高めになりますが、お腹の調子を優先するなら試す価値は十分にあります。また、大豆由来のソイプロテインやえんどう豆から作られるピープロテインといった植物性の製品も乳糖を一切含まないため、優れた選択肢といえます。
糖アルコール不使用の製品を選択
プロテインを飲んだ後のお腹の張りは、甘味料として使用される「糖アルコール」が原因かもしれません。具体的にはエリスリトールやキシリトールなどが該当し、多くのフレーバー付き製品でカロリーオフ甘味料として採用されています。これらの糖アルコールは小腸で消化・吸収されにくい性質を持つため、大腸で腸内細菌によって発酵し、ガスを発生させてしまうのです。
このガスが、腹部膨満感やゴロゴロ感の直接的な引き金となります。対策としては、購入前に製品パッケージ裏面の原材料名表示を必ず確認しましょう。「マルチトール」や「ソルビトール」、「還元水飴」といった表記がない製品を選ぶことが重要です。
最近ではステビアや羅漢果(ラカンカ)といった天然由来の甘味料を使用した製品も増えていますので、それらを選ぶか、甘味料を一切含まないプレーンタイプを選択するのも有効な方法でしょう。
消化に優しい植物性プロテインの活用
プロテイン摂取後のお腹の張りが気になる場合、消化に優しい植物性プロテインを活用するのが有効な選択肢となります。ホエイプロテインのような乳製品由来のプロテインに含まれる「乳糖」が原因で不調が起こる、いわゆる乳糖不耐症の方には特に試していただきたいです。
代表的なものに、大豆が原料の「ソイプロテイン」があり、必須アミノ酸のバランスを示すアミノ酸スコアが100と栄養価も申し分ありません。また、近年ではエンドウ豆由来の「ピープロテイン」も人気で、鉄分が豊富なうえアレルギーの心配が少ないという特長を持っています。
これら植物性のプロテインは、製品によっては食物繊維を含むものもあり、比較的ゆっくりと消化・吸収されるため胃腸への負担を軽減できるでしょう。まずは1食分から、ご自身の体質に合うか確かめてみることをおすすめします。
プロテイン摂取時の工夫で快適に

プロテインによるお腹の張りは、飲み方を少し工夫するだけで改善できる可能性があります。一気に飲むのではなく時間をかけてゆっくり摂取したり、冷たい飲み物で割るのをやめたりするだけで、胃腸への負担は驚くほど軽減されるでしょう。こうした簡単な習慣の見直しが、あなたの不快感を解消する第一歩です。
なぜなら、一度に大量のタンパク質が胃腸に送り込まれると、消化器官に大きな負荷がかかってしまうから。特にトレーニング直後などは消化機能が低下しがちなため、急いで摂取すると消化不良を招きやすくなります。さらに、冷たい液体は胃の働きを鈍らせ、お腹の不快な張りやゴロゴロ感の直接的な原因にもなり得るのです。
具体的には、トレーニング後に飲むとしても、一気飲みは避けて5~10分ほどかけてゆっくりと味わってみましょう。また、シェイカーに入れる水は、冷蔵庫から出したてのものではなく、常温に近い温度のものを使うのがおすすめです。

ゆっくり飲むことで消化を助ける
プロテインを水のように一気に飲むと、胃腸に大きな負担がかかります。一般的なプロテイン1食分に含まれる約20gから30gものタンパク質が一度に胃へ送り込まれると、消化の準備が追いつかなくなることがあるのです。
特に、胃酸や消化酵素の分泌が間に合わない場合、未消化のタンパク質が腸に流れ込み、悪玉菌のエサとなってガスが発生するため、お腹が張る原因になると考えられています。これを防ぐには、食事と同じように時間をかけて飲む意識が何より大切です。
例えば、シェイカーに入れた200mlから300mlのプロテインを、最低でも5分から10分かけて少しずつ口に運んでみましょう。トレーニング後で喉が渇いていても一気飲みは避け、数回に分けて飲むだけでも体感は大きく変わるはずです。ゆっくり摂取することが、スムーズな消化吸収を促し、不快な膨満感を和らげる鍵となります。
泡立ちを抑えるシェイク方法
プロテインをシェイクした際に立つ過剰な泡は、お腹が張る原因の一つと考えられています。泡と一緒に余分な空気を飲み込んでしまうため、ガスが溜まりやすくなるのです。しかし、シェイク方法を少し工夫するだけで、この泡立ちを大幅に抑えることが可能になります。まず試してほしいのが、シェイカーの振り方でしょう。
上下に激しく振るのではなく、手首のスナップを効かせて円を描くように横回転させると、空気の混入が少なくなり泡立ちが落ち着きます。また、シェイカーに300mlほどの水を先に入れ、その後にプロテインパウダー30gを加えるという基本的な手順を守るだけでも、ダマと泡立ちを軽減できるはずです。
時間に余裕があるなら、飲む30分ほど前に作って冷蔵庫で休ませておくのも非常に効果的な方法といえます。こうすることで自然に泡が消え、口当たりもまろやかになります。これらの簡単な工夫で、お腹の不快感を和らげ、快適にプロテインを摂取してください。
プロテインと腸内環境の関係

プロテインを飲んだ後のお腹の張りは、あなたの腸内環境が乱れているサインかもしれません。身体作りのために良かれと思って摂取したプロテインが、かえって腸に負担をかけてしまうことがあるのです。特に、一度に大量に摂取したり、ご自身の体質に合わない種類を選んだりすると、不快な症状につながりやすいでしょう。
まずはプロテインと腸の深い関係性を知ることが、快適なプロテインライフへの第一歩です。なぜプロテインが腸内環境に影響を与えるのでしょうか。その大きな理由として、消化しきれなかったタンパク質が腸内で悪玉菌のエサになってしまう点が挙げられます。私たちの腸内には善玉菌や悪玉菌など、多種多様な細菌が生息し、そのバランスを保っている状態でした。
しかし、タンパク質が過剰になると、このバランスが崩れ、悪玉菌が優勢になってしまうのです。具体的には、悪玉菌が増えることで腸内でガスが発生しやすくなり、お腹の張りや不快感の原因となります。また、ホエイプロテインに含まれる「乳糖」をうまく分解できない乳糖不耐症の方が、お腹のゴロゴロを感じるのも腸内環境が関係した一例。

オリゴ糖ケストースの整腸効果
プロテイン摂取後のお腹の張りに悩むなら、腸内環境を整えるオリゴ糖「ケストース」が役立つかもしれません。ケストースは、ビフィズス菌や酪酸菌といった善玉菌のエサとなるプレバイオティクスとして優れた働きをします。
プロテインのタンパク質が腸内で悪玉菌のエサとなり、不快なガスを発生させることがありますが、ケストースを同時に摂取することで善玉菌が優位な状態を作り出すのです。実際に、1日わずか1gのケストース摂取でも、善玉菌であるビフィズス菌を増やす効果が研究で確認されています。
腸内フローラのバランスが整うと、悪玉菌の活動が自然と抑制され、ガスの発生やお腹の張りが軽減される仕組みです。ケストースはタマネギやアスパラガスにも含まれる天然由来のオリゴ糖であり、安心して日々のプロテイン生活に取り入れられる点も大きな魅力でしょう。
善玉菌を増やす食事の工夫
プロテイン摂取後のお腹の張りを和らげるには、腸内の善玉菌を増やす食生活が有効です。善玉菌のエサとなる水溶性食物繊維とオリゴ糖を意識的に摂取しましょう。水溶性食物繊維は、わかめやめかぶなどの海藻類、ごぼう、オクラに豊富であり、オリゴ糖は玉ねぎ、にんにく、そして納豆や味噌といった大豆製品に多く含まれています。
さらに、善玉菌そのものを直接取り入れる「プロバイオティクス」も重要です。例えば、ビフィズス菌BB536を含むヨーグルトや、植物性乳酸菌が豊富なキムチ、ぬか漬けといった発酵食品を毎日の食卓に加えてみてください。
朝食に食べるヨーグルトへ、オリゴ糖を含むバナナやりんごを少量トッピングするだけでも、手軽に腸内環境の改善が期待できるでしょう。
プロテイン摂取に関するよくある質問

プロテインを飲む際、お腹の張り以外にも「いつ飲むのがベスト?」「1日にどれくらい飲めばいい?」といった様々な疑問が浮かぶことがあります。多くの方が抱えるこうした細かな悩みを解消することが、プロテインを効果的に活用する第一歩です。ここでは、プロテイン摂取に関するよくある質問に答え、あなたの疑問をスッキリ解消していきましょう。
なぜなら、プロテインはただ闇雲に飲んでも、期待する効果は得られにくいからです。あなたの目的やライフスタイルに合ったタイミングや量を知ることで、初めてその価値を最大限に引き出すことができます。間違った知識で続けてしまうと、体に不要な負担をかけてしまう可能性も否定できません。
例えば、「運動後30分以内に飲むゴールデンタイムは本当に重要なのか」「朝食をプロテインに置き換えても大丈夫?」といったタイミングに関する質問。また、「1日の摂取量の上限は?」「就寝前に飲むと太るというのは本当?」など、量や体重管理にまつわる疑問も多く寄せられます。

プロテインで下痢になるのはなぜ?
プロテイン摂取後に下痢が起こる場合、主な原因として「乳糖不耐症」が考えられます。特に牛乳由来のホエイプロテインの中でも、WPC(ホエイプロテインコンセントレート)と呼ばれる製品には乳糖が多く残っているのです。
日本人の成人の約7割は、乳糖を分解する消化酵素「ラクターゼ」の活性が低いとされており、分解しきれない乳糖が大腸に達することで腹痛や下痢を引き起こすことがあります。次に、スクラロースやアセスルファムKといった「人工甘味料」も一因でしょう。
これらの成分は小腸で吸収されにくく、腸内の浸透圧を高める性質があるため、結果として浸透圧性の下痢につながるケースも少なくありません。さらに、一度に30gを超えるようなタンパク質の過剰摂取は消化不良を招いたり、冷たい牛乳や水で飲むことが胃腸の機能を低下させたりすることも、下痢の誘因になると言えます。
プロテインの飲み過ぎは腎臓に悪い?
プロテインの過剰摂取が腎臓へ負担をかける、という説は本当なのでしょうか。結論から言うと、健康な方が適量を摂取する分には問題ありませんが、過剰摂取はリスクを高める可能性があります。タンパク質は体内で分解される際、尿素などの窒素老廃物を生成する仕組みです。
この老廃物を血液中から濾過し、尿として排出するのが腎臓の役割。そのため、プロテインの飲み過ぎでタンパク質の摂取量が極端に増えると、腎臓の濾過作業が過重になり、長期的に機能へ影響を及ぼす恐れが指摘されているのです。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、成人男性の1日の推奨量は65g、女性は50gと定められています。トレーニングで体重1kgあたり2.0g以上を目指す場合も、食事からの摂取量と合わせて計算することが大切でしょう。もともと腎機能に不安がある方は、利用前に必ず医師へ相談してください。
プロテインの保存方法と注意点
プロテインによるお腹の張りは、不適切な保存方法が原因かもしれません。粉末プロテインは湿気や熱、直射日光に弱いため、開封後は必ず冷暗所で保管しましょう。キッチンのコンロ周りは避け、袋の口をしっかり閉じるか密閉容器に移し替えるのがおすすめです。
これにより、品質劣化だけでなくダニの侵入・繁殖も防げます。開封後は1〜3ヶ月を目安に使い切るようにしてください。冷蔵庫での保管は、出し入れの際に生じる温度差で結露し、粉末が固まる原因になるため注意が必要です。また、水に溶かしたプロテインを放置することもやめましょう。
特に気温25℃を超える夏場は雑菌が繁殖しやすく、作ってから30分以内に飲み切るのが鉄則。正しい保存と摂取を心がけることで、お腹の不調を未然に防げるのです。
まとめ:もう悩まない!プロテインでお腹が張る原因と対策

今回は、プロテインを飲むとお腹が張ってしまいお困りの方に向けて、
- プロテインでお腹が張る主な原因
- 原因に応じた具体的な対策方法
- お腹が張りにくいプロテインの選び方
上記について、解説してきました。
プロテインによるお腹の張りは、原因を正しく理解し対処すれば、十分に改善が期待できます。なぜなら、乳糖や人工甘味料、飲む量やタイミングなど、原因は一つではないからです。これまで不快な症状に悩まされてきた方も、諦める必要は全くありません。
まずはこの記事を参考に、ご自身の生活習慣や飲んでいるプロテインを振り返ってみましょう。そして、自分にできそうな対策から一つずつ試してみることが、解決への第一歩となります。理想の体を目指してプロテインを取り入れてきた、これまでのあなたの頑張りは大変価値のあるものです。
お腹の不調でその努力を中断してしまうのは、非常にもったいないことでした。しかし、もう大丈夫です。原因と対策を知った今、お腹の不快感に悩まされることなく、安心してトレーニングに集中できる未来が待っています。