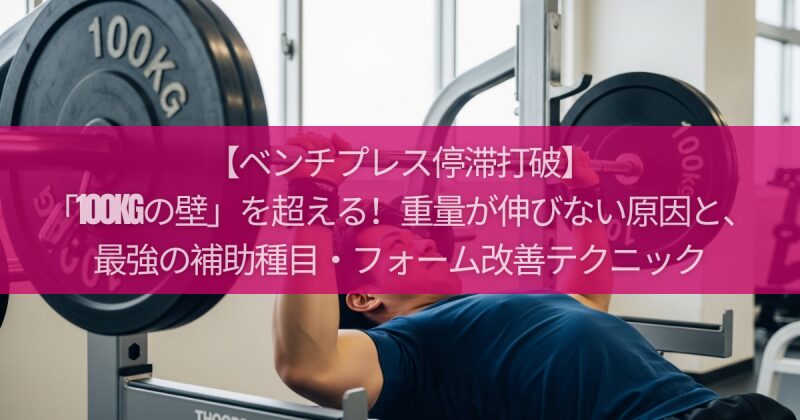「ベンチプレス、60kgから全然重量が伸びない…。才能ないのかな…」
「週2回も胸トレしてるのに、なんで停滞するんだ!?何が間違ってる?」
「男なら、やっぱり『ベンチプレス100kg』を挙げたい!でも、今のままじゃ到底無理そうだ…。どうすればあの壁を越えられる?」
ジムのフリーウェイトエリアで、多くのトレーニーが情熱を注ぐ「キング・オブ・上半身トレーニング」、ベンチプレス。
しかし、その人気とは裏腹に、多くの人が「ある一定の重量」からピタリと成長が止まる「停滞期(プラトー)」に悩まされています。
特に、「100kgの壁」は、多くの男性トレーニーにとって、憧れであり、同時に高い壁として立ちはだかります。
「頑張っているのに、なぜか伸びない…」
その原因は、あなたの才能の限界ではありません。
ほとんどの場合、それは「フォームの細かな間違い」「トレーニングプログラムのマンネリ化」、あるいは「補助筋の弱さ」といった、明確な原因が潜んでいるのです。
この記事は、ベンチプレスの重量が伸び悩んでいる、すべてのトレーニーのための「停滞打破ガイド」です。
なぜあなたのベンチプレスが停滞するのか、その5つの主な原因を徹底分析。
さらに、停滞を打ち破るための「フォーム改善8つのチェックポイント」と、ベンチプレスを劇的に強くする「最強の補助種目5選」まで、具体的な処方箋を徹底解説します。
もう停滞に悩むのは終わりです。

この記事でわかること
- なぜ多くの人がベンチプレスで「停滞(100kgの壁)」にぶつかるのか
- あなたのベンチプレスが伸びない5つの根本的な原因
- 停滞を打破するための具体的な「フォーム改善チェックポイント」と「最強の補助種目」
なぜベンチプレスは停滞しやすいのか?「100kgの壁」の正体

ベンチプレスは、スクワットやデッドリフトと並び「BIG3」と呼ばれる基本種目ですが、その中でも特に停滞しやすい種目と言われます。
なぜでしょうか?
① フォームの習得が難しい(肩甲骨、ブリッジ、軌道)
ベンチプレスは、一見「寝てバーを上げ下げするだけ」の単純な動作に見えます。
しかし、その実態は、「肩甲骨の固定」「ブリッジ(アーチ)の構築」「足の力(レッグドライブ)」「バーの正しい軌道」など、非常に多くの高度なテクニックが要求される、全身運動なのです。
これらのどれか一つでも欠けていると、効率よく力を発揮できず、すぐに頭打ちになります。
② 「胸」だけでなく「肩(前部)」「三頭筋」も関わる複合動作
ベンチプレスは、主に「大胸筋(胸)」を鍛える種目ですが、同時に「三角筋前部(肩)」と「上腕三頭筋(腕の裏側)」も強力に動員されます。
もし、この「補助筋」である肩や三頭筋が、メインの胸筋に比べて弱すぎると、それがボトルネックとなり、全体の重量が伸び悩むのです。
③ 間違ったフォームでの「エゴリフティング」による頭打ち
「100kg」という数字は、多くのトレーニーにとって魔力を持っています。
その重さを求めるあまり、フォームを無視し、お尻をベンチから浮かせたり、反動を使ったり、可動域を狭くしたりする「エゴリフティング(見栄のためのトレーニング)」に陥りがちです。
間違ったフォームで一時的に重量が伸びても、それは筋肉の成長ではなく、怪我のリスクを高めているだけ。
すぐに本当の停滞が訪れます。
【原因分析】あなたのベンチプレスが「伸びない」5つの理由

あなたの停滞の原因は、以下のどれかに当てはまる可能性が非常に高いです。
冷静に自己分析してみましょう。
① フォームが崩れている(肩甲骨が寄っていない、ブリッジが低い、手首が寝ている等)
これが最大の原因です。
特に「肩甲骨の固定(寄せて下げる)」ができていないと、力が肩に逃げてしまい、胸に効かないばかりか、肩を痛める原因になります。
後述する「8つのチェックポイント」で、あなたのフォームを徹底的に見直してください。
② トレーニング頻度・ボリュームが不適切(やりすぎorやらなすぎ)
・やりすぎ:早く強くなりたい一心で、週に3回も4回も高強度でベンチプレスを行っていませんか?
回復が追いつかず、オーバートレーニングになっている可能性があります。
・やらなすぎ:週に1回、数セットだけでは、筋力向上のための刺激(ボリューム)として単純に不足している可能性があります。
③ 「補助筋」(特に三頭筋・肩)が弱すぎる
ベンチプレスは「押す」動作です。
バーを押し上げる最終局面では、「上腕三頭筋」の強さが決定的に重要になります。
また、動作全体を通して「三角筋前部(肩)」も使われます。
胸筋は強いのに、これらの補助筋が弱いと、そこで力が尽きてしまい、高重量が挙がりません。
④ プログレッシブオーバーロードが実践できていない(記録不足・マンネリ)
「いつも同じ重量、同じ回数」で満足していませんか?
筋肉は「適応」します。
トレーニング記録をつけ、前回よりも「1kgでも重く」あるいは「1回でも多く」挙げるという「プログレッシブオーバーロード」を実践できていなければ、筋肉が成長する理由はありません。
⑤ 栄養(カロリー・タンパク質)&休養が足りていない
見落としがちな基本です。
筋力を向上させ、筋肉を成長させるためには、「オーバーカロリー」の食事と、十分な「タンパク質」(体重×2g目安)、そして「質の高い睡眠」が不可欠です。
減量中でカロリーが不足している状態では、筋力が伸び悩むのは当然とも言えます。
【フォーム再点検】停滞を打ち破る「8つの重要チェックポイント」

ベンチプレス100kgの壁を超えるためには、パワーを最大化し、怪我を防ぐ「完璧なフォーム」が必須です。
バーだけで良いので、以下の8点を一つずつ確認してみてください。
① 5点支持(頭・肩・尻・両足)はできているか?
ベンチプレス中、頭、両肩(肩甲骨)、お尻、そして両足の裏の「5点」が、ベンチや床に常にしっかりと接地していなければなりません。
特に、動作中にお尻が浮いたり、足がバタついたりするのはNGです。
② 「肩甲骨の内転・下制」(寄せて下げる)はセット中維持できているか?
これが最重要です。
バーをラックアップする前に、両方の肩甲骨を「背骨に寄せて(内転)」「お尻の方向に下げる(下制)」。
この「胸を張った」状態を、セットが終了するまで絶対に解いてはいけません。
これが肩の怪我を防ぎ、大胸筋を最大限に使うための土台となります。
③ 適切な「ブリッジ(アーチ)」は組めているか?(腰を反らすのではない)
「ブリッジ」は、肩甲骨と尻をベンチにつけたまま、背中(胸椎)を反らせてアーチを作ることです。
(「腰(腰椎)」を無理に反らせるのとは違います)
適切なブリッジは、肩甲骨の固定を助け、バーの挙上距離を短くし、より高重量を扱えるようにするテクニックです。
④ グリップ幅は適切か?手首は寝ていないか?
・グリップ幅:肩幅より少し広め(81cmラインに人差し指や中指が目安)が一般的。
幅が狭すぎると三頭筋への負荷が、広すぎると肩への負荷が強まります。
・手首:バーベルの重みで手首が甲側に寝て(反って)しまうと、力が逃げ、手首を痛める原因になります。
親指の付け根(母指球)あたりでバーを握り、手首を立てる(もしくは少しだけ寝る程度)意識を持ちましょう。
⑤ バーの「軌道」は正しいか?(胸の下部へ下ろし、斜め上へ)
バーベルは、真下に下ろして真上に上げるのではありません。
「みぞおち〜胸の下部」あたりに向かって「斜め下」に下ろし、上げる時は「肩の真上」に向かって「斜め上」に押し上げます。
(軌道は「ハ」の字、あるいは「J」の字を描くイメージ)
首や肩の真上に下ろすのは危険です。
⑥ 呼吸法(バルサルバ法)はできているか?
高重量を扱う際は、呼吸法も重要です。
バーを下ろす時に大きく息を吸い込み、息を止めたまま(腹圧を高めたまま)バーを押し上げ、最もキツい局面を通過してから「フッ」と息を吐きます。
(バルサルバ法)
⑦ 「脚の力(レッグドライブ)」を使えているか?
ベンチプレスは上半身だけの運動ではありません。
両足で床をしっかりと踏みしめ、バーを押し上げる瞬間に、床を「蹴る(押し込む)」力(レッグドライブ)を使うことで、上半身のパワーをさらにブーストさせることができます。
尻が浮かない範囲で、下半身の力も連動させましょう。
⑧ 毎回「フルレンジ(胸まで下ろす)」でやっているか?
高重量を扱いたいがために、胸まで数センチのところで切り返す「浅い」ベンチプレスになっていませんか?
それは可動域を制限した「パーシャルレップ」であり、筋肥大効果も筋力向上効果も半減します。
必ず、毎回バーが「胸に軽く触れる(またはスレスレ)」まで下ろし、そこからしっかりと押し上げる「フルレンジ」を心がけましょう。
「肩甲骨」を固定したら、10kg伸びた
僕は、ベンチプレスが80kgで完全に停滞していました。
それ以上を目指すと、なぜか胸よりも肩が痛くなる。
フォーム動画をスマホで撮影してみると、衝撃の事実が発覚しました。
バーを下ろす時に、胸を張っているつもりが、重さに負けて肩甲骨が開き、肩が前にすくんでいたのです。
これでは胸に効くはずがなく、肩を痛めるのも当然でした。
僕はプライドを捨て、60kgまで重量を落とし、「肩甲骨を寄せて、下げる」という動作だけを徹底的に練習しました。
ベンチに肩甲骨を「突き刺す」ようなイメージです。
そのフォームが固まった1ヶ月後、恐る恐る85kgに挑戦…挙がった!
さらに、その勢いで90kgもクリア。
たった一つの「肩甲骨の固定」というテクニックをマスターしただけで、僕の停滞は嘘のように打ち破られました。
ベンチプレスは、いかに「土台」が重要かを痛感しました。
ベンチプレスを強化する「最強の補助種目」5選

フォームが正しいのに停滞している場合、あなたの「弱い部分(ボトルネック)」を強化する「補助種目」を取り入れるのが非常に効果的です。
① ダンベル・ベンチプレス(可動域と安定性の強化)
バーベルと違い、左右のダンベルを個別にコントロールする必要があるため、安定筋が鍛えられます。
また、バーベルよりも深く下ろせるため、大胸筋の可動域全体に強烈なストレッチ刺激を与えることができます。
② インクライン・ダンベルプレス(大胸筋上部の強化)
ベンチに角度をつけて(インクライン)、ダンベルプレスを行います。
多くの人が弱いとされる「大胸筋上部」をピンポイントで強化できます。
胸板の「厚み」を作る上でも欠かせません。
③ ディップス(大胸筋下部と三頭筋の強化)
上半身のスクワットとも呼ばれる最強の自重(または加重)種目。
大胸筋の下部と、上腕三頭筋を同時に鍛え上げます。
ベンチプレスの「押し込む力」を強力にサポートします。
④ ナローグリップ・ベンチプレス(三頭筋とプレス力の強化)
ベンチプレスのグリップ幅を「狭く(肩幅程度)」して行うバリエーション。
バーを押し上げる最終局面で使われる「上腕三頭筋」を集中的に鍛えることができます。
「あと一押しが弱い」と感じる人に最適です。
⑤ ショルダープレス(肩前部の強化)
バーベルやダンベルを頭上に持ち上げる種目。
ベンチプレスでも使われる「三角筋前部(肩)」を強化し、プレス動作全体の土台を強くします。
停滞期打破のための「プログラム見直し」テクニック
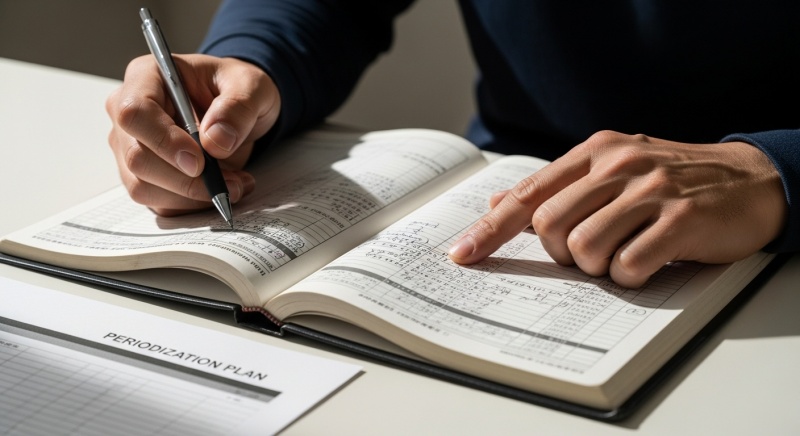
フォームも補助種目もやっているのに停滞する場合、プログラム自体がマンネリ化している可能性があります。
① 頻度・ボリュームの見直し(例:週1回 → 週2回にする)
筋力向上には「頻度」も重要です。
もし週1回しかベンチプレス(胸トレ)を行っていないなら、週2回に増やしてみましょう。
(例:月曜は高重量メイン、木曜は高回数メインなど)
回復が追いつく範囲で、総トレーニングボリューム(重量×回数×セット数)を増やすことが、停滞打破の鍵となります。
② ピリオダイゼーション(期分け)の導入(高重量期と高回数期)
毎回MAX重量に挑戦するような高強度トレーニングばかり続けていると、神経系が疲労し、停滞しやすくなります。
そこで、意図的にプログラムを「期分け」するテクニックが有効です。
・筋力期:3〜5回しかできない高重量を扱う期間(例:4週間)
・筋肥大期:8〜12回できる中重量を扱う期間(例:4週間)
このように刺激の種類を変えることで、筋肉と神経系に新たな適応を促し、長期的な成長を引き出します。
③ 意図的な「ディロード(負荷軽減)」の実施
停滞の原因が、単純な「疲労の蓄積」である場合も多いです。
「ディロード」とは、1週間程度、意図的にトレーニングの強度(重量やセット数)を大幅に下げる、あるいは完全に休む期間のこと。
これにより、蓄積した疲労がリセットされ、体がフレッシュな状態に戻り、ディロード明けに再び成長が始まることがあります。
「休む勇気」も、停滞打破の重要な戦略です。
「三頭筋」が僕のボトルネックだった
僕は、ベンチプレス100kgの壁に挑み続けていました。
胸まで下ろし、そこから半分までは押し上げられる。
しかし、最後の「もう一押し」ができずに、いつも潰れていました。
「胸の力が足りないんだ!」と思い込み、ダンベルフライなど胸の種目ばかりを追加していました。
しかし、停滞は続く。
悩んだ末、パーソナルトレーナーに相談すると、意外な答えが返ってきました。
「〇〇さんは、胸は強いですよ。
弱いのは、最後の押し込みで使う『三頭筋』です」。
盲点でした。
僕は、プログラムに補助種目として「ナローグリップ・ベンチプレス」と「ディップス」を週1回、追加しました。
三頭筋を集中的に強化すること1ヶ月半。
再び100kgに挑戦。
いつもなら失速するはずの局面を、腕の力で「グッ」と押し込むことができ…ついに、バーは上がりきりました。
僕の停滞の原因(ボトルネック)は、胸ではなく、「三頭筋」という補助筋の弱さだったのです。
自分の弱点を正確に知ることの重要性を痛感しました。
まとめ:停滞は「成長のサイン」。原因を見つけて100kgの壁を越えよう

ベンチプレスの停滞は、決して「才能の限界」ではありません。
それは、あなたの体が「今のやり方では、もう成長できませんよ。
何かを変えてください」と送っている、ポジティブな「サイン」なのです。
そのサインを受け取ったら、この記事で紹介した項目を一つずつチェックしてみてください。
- 原因を分析:フォーム?頻度?補助筋?栄養?休養?
- フォームを再点検:8つのチェックポイントは完璧か?特に「肩甲骨の固定」は?
- 補助種目を追加:自分の弱点(三頭筋?肩?)を強化する種目を導入する。
- プログラムを見直す:頻度やボリューム、期分け(ピリオダイゼーション)を検討する。
- 記録を続ける:プログレッシブオーバーロードを確実に実践する。
- 栄養と休養を見直す:増量期ならカロリーは足りているか?睡眠は十分か?
停滞の原因を特定し、それを修正するための「正しい努力」を積み重ねれば、あなたのベンチプレスは必ず再び伸び始めます。
「100kgの壁」は、決して越えられない壁ではありません。
それは、あなたが「初心者」から「中級者」へとレベルアップするために、乗り越えるべき「課題」なのです。