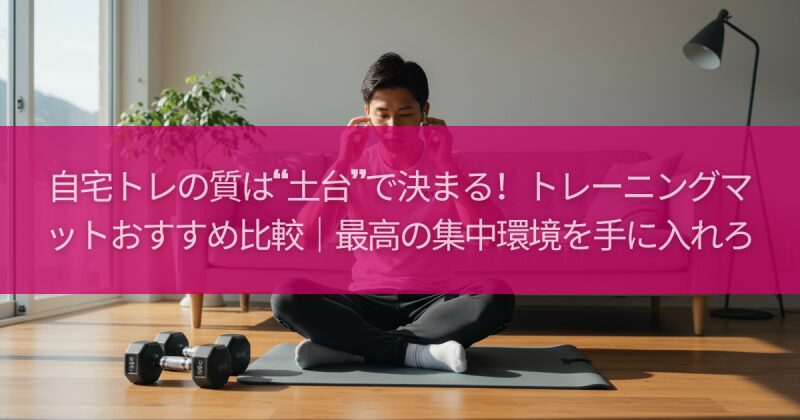「ダンベルを床に置くたび、傷つかないかヒヤヒヤする…」
「マンションだから、トレーニング中の振動や音が下の階に響いていないか心配…」
「ヨガマットで代用してるけど、汗で滑るし、なんだか安定しない…」
その一瞬の不安や不快感が、あなたの集中力を奪い、トレーニングの質を下げているとしたら、それは非常にもったいないことです。
あなたがダンベルやベンチにこだわるように、その力を受け止める「土台」にこだわることこそが、実はトレーニング効果を最大化する隠れた秘訣なのです。
その最高の土台となるのが、「トレーニングマット」です。
この記事では、「ヨガマットじゃダメなの?」という根本的な疑問から、あなたのトレーニングスタイルに完璧にマッチする一枚を見つけ出すための科学的な選び方、そして目的別に厳選した最新のおすすめモデルまでを徹底解説します。

この記事でわかること
- なぜ筋トレにヨガマットではなく「トレーニングマット」が必須なのかという決定的理由
- 厚み・素材・サイズで比較する、後悔しないトレーニングマットの選び方
- あなたの目的に合った最新のおすすめ人気ランキングTOP12
【結論】筋トレに「ヨガマット」はNG!トレーニングマットが必要な3つの決定的理由

「マットなんてどれも同じでしょう?」そう考える人も少なくありません。
しかし、ヨガマットとトレーニングマットは、似て非なるもの。
その目的と設計思想は全く異なり、筋トレにヨガマットを使用することは、多くのデメリットとリスクを伴います。
理由1:器具の重さに耐える「防傷性」と「耐久性」が全く違う
ヨガマットは、基本的に自重(人間の体重)のみを想定して作られています。
そのため、ダンベルの角やトレーニングベンチの脚部など、局所的に強い圧力がかかると簡単にへこみ、破れてしまいます。
一方、トレーニングマットは高重量の器具の使用を前提に、高密度・高耐久な素材で作られており、あなたの家の床を傷やへこみから確実に守ってくれるのです。
理由2:衝撃を吸収する「クッション性」と階下への「防音性」が段違い
ヨガマットのクッション性は、あくまでポーズをとる際の快適性を目的としています。
しかし、トレーニングマットのそれは、ダンベルを置いた時の衝撃や、ジャンプ系トレーニング(HIITなど)の着地衝撃を吸収し、振動を軽減するためにあります。
この衝撃吸収能力の差が、マンションなどで特に気になる階下への騒音(振動音)を抑制する「防音性」の決定的な違いとなって現れるのです。
理由3:高重量でも沈み込まない「安定性」と汗でも滑らない「グリップ力」
柔らかすぎるヨガマットの上で高重量のスクワットを行うと、足元が沈み込んでしまい、フォームが安定しません。
これはパフォーマンスの低下だけでなく、バランスを崩して怪我をするリスクにも繋がります。
トレーニングマットは、適度な硬さで体をしっかり支え、安定した土台を提供します。
また、表面に施された凹凸加工により、汗で濡れても滑りにくい高いグリップ力を発揮し、安全なトレーニングをサポートします。
「これくらい大丈夫」が招いた後悔…Gさんの体験談
Gさんは、自宅トレーニングを始める際に「マットは家にあるヨガマットでいいや」と安易に考えていました。
トレーニング自体は問題なくできていましたが、ある日、少し疲れてダンベルを床に「ドン」と置いてしまったのです。
慌ててヨガマットをめくると、フローリングにはくっきりとダンベルの形のへこみが。
「専用のマットを買っておけば…」と後悔しても時すでに遅し。
彼は修理費用という高い代償を払い、「土台」への投資の重要性を痛感したそうです。
後悔しないトレーニングマットの選び方|5つの最重要ポイント

トレーニングマットの世界は、厚み、素材、サイズと非常に奥が深いものです。
あなたのトレーニング環境を最高のものにするための、5つの選択基準を詳しく見ていきましょう。
ポイント1:トレーニング内容で選ぶ「厚み」|自重なら10mm、器具トレなら15mm以上?
マットの厚みは、クッション性、防音性、安定性を左右する最も重要な要素です。
あなたの主なトレーニング内容が、最適な厚みを選ぶための最も重要な指針となります。
- ~10mm厚:腹筋や腕立て伏せなどの自重トレーニング、ストレッチがメインの方におすすめ。
適度な硬さで動きやすく、収納性も高いです。 - 10mm~20mm厚:ダンベルトレーニングやHIITなど、器具の使用やジャンプ系の動作がある方におすすめ。
クッション性と安定性のバランスが良く、最も人気の厚みです。 - 20mm厚~/ゴム製マット:トレーニングベンチや懸垂マシンなど、大型器具を設置する場合や、高重量を扱う本格的なホームジムを目指す方におすすめ。
圧倒的な耐久性と防音性を誇ります。
ポイント2:特徴で選ぶ「素材」|PVC・NBR・TPE・EVA・ゴムの違いを完全理解
素材によって、価格、耐久性、重さ、匂いなどが大きく異なります。
それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを選びましょう。
| 素材 | 特徴 |
|---|---|
| PVC (ポリ塩化ビニル) | ・安価で耐久性が高い ・グリップ力に優れる ・やや重く、特有の匂いがある場合も |
| NBR (ニトリルゴム) | ・柔らかくクッション性が非常に高い ・軽量で持ち運びに便利 ・器具の重みによるへこみが残りやすい |
| TPE (熱可塑性エラストマー) | ・ゴムのような弾力性とプラスチックの耐久性を併せ持つ ・軽量で水に強く、手入れが簡単 ・環境に優しく、匂いも少ないが比較的高価 |
| EVA (エチレン酢酸ビニル) | ・非常に軽量で、弾力性と耐久性のバランスが良い ・ジョイントマットの主流素材 ・水や汚れに強く、手入れが楽 |
| ゴム | ・圧倒的な耐久性、防音性、安定性 ・ジムなどでも使用される本格仕様 ・非常に重く高価で、ゴム特有の匂いが強い |
ポイント3:器具の配置で選ぶ「サイズ」|大判ジョイント式 vs 一枚式ロールタイプ
マットの形状は大きく分けて2種類あります。
一枚式(ロールタイプ)は、さっと広げてすぐに使え、丸めてコンパクトに収納できるのがメリットです。
一方、ジョイント式は、部屋の形に合わせて自由にレイアウトでき、トレーニングエリア全体をカバーできるのが最大の強みです。
トレーニングベンチや懸垂マシンを設置するなら、沈み込みの少ない硬めのジョイント式がおすすめです。
ポイント4:「防音性」を最重視するなら「硬さ・重さ・素材」をチェック
マンションなどで防音性を第一に考える場合は、「厚み」だけでなく「素材の密度(硬さ・重さ)」が重要になります。
柔らかく軽いマットは衝撃を吸収しますが、重量物の振動(重低音)は防ぎきれません。
より高い防音性を求めるなら、高密度なEVAや、最強の防音性を誇るゴム製のマットを選ぶと良いでしょう。
ポイント5:意外と重要!「収納性」と「手入れのしやすさ」
トレーニングのたびにマットを出し入れする場合、軽さや、丸めた際にまとめるストラップが付属しているかなどの「収納性」もチェックしましょう。
また、汗を多くかくトレーニングをするなら、水拭きができるか、速乾性があるかなど、「手入れのしやすさ」も長く清潔に使うための重要なポイントです。
【2025年最新】目的・タイプ別!トレーニングマットおすすめ人気ランキング12選

ここからは、5つの選び方を踏まえ、あなたのトレーニングスタイルに最適なモデルをランキング形式でご紹介します。
この中から、あなたのトレーニング空間を完璧にサポートする最高の一枚を見つけ出してください。
【一枚式・ロールタイプ】手軽&万能モデルTOP6
【1位】GronG (グロング) トレーニングマット 10mm
特徴:高品質なNBR素材を使用し、クッション性と耐久性のバランスが絶妙。
丸めてコンパクトに収納できる手軽さから、自重トレーニングやストレッチがメインのユーザーに絶大な人気を誇る。
品質と価格のバランスが取れた鉄板モデル。
【2位】LEADING EDGE (リーディングエッジ) トレーニングマット
特徴:PVC素材を採用し、器具の使用にも耐える高い耐久性とグリップ力が魅力。
重量があるため安定感も抜群で、ダンベルを使ったトレーニングでもマットがズレにくい。
本格的なトレーニングの第一歩として最適。
【3位】adidas (アディダス) トレーニングマット
特徴:有名スポーツブランドならではの、洗練されたデザインと確かな品質。
やや薄手ながら高密度な素材で、安定性とクッション性を両立。
トレーニングのモチベーションを高めてくれる一枚。
【4位】YouTen (ユーテン) トレーニングマット 15mm/20mm
特徴:15mm、20mmという極厚のラインナップが魅力。
クッション性を最重視し、膝や肘をつくトレーニングが多い人や、ジャンプ系の運動(HIITなど)を行うユーザーに最適。
圧倒的な柔らかさで体を守る。
【5位】Gruper (グルーパー) ヨガマット 15mm
特徴:「ヨガマット」と名付けられているが、その15mmの厚みと高密度NBR素材は筋トレにも十分対応可能。
横縞のエンボス加工が滑りを防ぎ、優れたグリップ力を発揮。
カラーバリエーションが豊富なのも嬉しいポイント。
【6位】Amazonベーシック エクササイズマット
特徴:驚異的なコストパフォーマンスと、必要十分な機能を両立したモデル。
13mmの厚みがあり、基本的なトレーニングには問題なく使用可能。
「とにかく安く、でも最低限の品質は欲しい」というニーズに応える。
【大判・ジョイント式】本格ホームジム向けモデルTOP6
【1位】IROTEC (アイロテック) ラバーマット
特徴:ジム品質の器具で定評のあるIROTECが手掛ける本格ラバーマット。
高重量のバーベルやダンベルを置いてもびくともしない圧倒的な耐久性と防音性を誇る。
ホームジムを作るなら最終的に行き着く最高峰のマット。
【2位】LEADING EDGE (リーディングエッジ) EVAジョイントマット 大判
特徴:大判サイズ(1m x 1m)で、広い面積を少ない枚数で敷き詰められるのが魅力。
十分な硬さがあり、トレーニングベンチや懸垂マシンを置いても沈み込みにくい。
カッターで簡単にカットでき、部屋の形に合わせやすいのも利点。
【3位】GronG (グロング) ジョイントマット
特徴:部屋のインテリアを邪魔しない、スタイリッシュなカラーリング(グレーやブラックなど)が人気。
サイドパーツが付属しており、端まで綺麗に敷き詰められる。
品質とデザイン性を両立したいユーザーにおすすめ。
【4位】Fighting Road (ファイティングロード) ジョイントマット
特徴:格闘技用品も手掛けるブランドならではの、衝撃吸収性に優れた高硬度EVA素材を使用。
激しいトレーニングでも安定感を損なわない。
リバーシブルカラーで、気分に合わせて部屋の雰囲気を変えられる。
【5位】MRG ジョイントマット 大判 10mm
特徴:10mmの厚みと手頃な価格で、広い範囲をカバーしたいユーザーに最適。
トレーニングエリア全体を保護したいが、コストは抑えたいというニーズに応える。
重量器具を置かないエリアでの使用に特に適している。
【6位】タンスのゲン ジョイントマット
特徴:家具メーカーならではの、品質管理と豊富なカラー・サイズ展開が魅力。
シックハウス症候群の原因物質を含まないなど、安全性への配慮も行き届いている。
トレーニングだけでなく、子供のプレイマットとしても使える汎用性を持つ。
トレーニングマットの効果を最大化する+αの知識

最高のマットを手に入れたら、その効果をさらに高めるための知識も身につけておきましょう。
より高い防音性を求めるなら「マットの二重敷き」も有効な手段
マンションなどでどうしても音が気になる場合は、マットの二重敷きが効果的です。
例えば、下に硬めのジョイントマットを敷き、その上でトレーニングするエリアにだけクッション性の高い一枚式マットを敷くなど、性質の違うマットを組み合わせることで、より高い防音性が期待できます。
特に集合住宅の場合、少しの工夫が大きな安心に繋がります。
汗や汚れはこまめに!清潔に長く使うためのメンテナンス方法
トレーニング後のマットは汗や皮脂で汚れています。
そのまま放置すると、匂いやカビの原因になることも。
トレーニング後は、固く絞ったタオルでさっと水拭きし、風通しの良い場所で乾かす習慣をつけましょう。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた水で拭くと効果的です。
トレーニングマットに関するよくある質問(Q&A)

最後に、トレーニングマットの購入を検討している方が抱きがちな、細かい質問にお答えします。
購入後の「こんなはずじゃなかった」を防ぐために、最後の疑問をここで解決しておきましょう。
- Q1. マットの上にトレーニングベンチや懸垂マシンを置いても大丈夫?
- A1. はい、大丈夫です。
むしろ、必ずマットの上に設置してください。
ただし、長期間同じ場所に置くとマットに跡が残ります。
特にクッション性の高いNBR素材はへこみやすいため、器具を置くなら硬めのEVA製ジョイントマットやゴムマットが最適です。 - Q2. マットのゴムの匂いが気になります。対策はありますか?
- A2. 特にPVCやゴム製のマットは、開封直後に特有の匂いがすることがあります。
ほとんどの場合は、数日間、風通しの良い場所に広げておくことで解消されます。
匂いに敏感な方は、TPE素材など、匂いが少ないことを謳っている製品を選ぶと良いでしょう。 - Q3. ジョイントマットの隙間にゴミが溜まりませんか?
- A3. 多少は溜まります。
しかし、ジョイントマットは汚れた部分だけを取り外して水洗いできるというメリットがあります。
定期的に掃除機をかけ、気になる部分は時々外して掃除することで、清潔な環境を保つことができます。
最高の「城」を手に入れたHさんの話
Hさんはこれまで、トレーニングのたびに一枚式のマットを敷き、終わったら丸めて片付ける…という作業が地味にストレスでした。
思い切って部屋の一角に硬めのジョイントマットを敷き詰め、自分だけのトレーニングスペースを常設。
いつでもすぐにトレーニングが始められる環境は、彼のモチベーションを劇的に向上させました。
「ここが俺の城です。
このスペースがあるだけで、『さあ、やるか!』という気持ちになるんです。
マットを敷いただけなのに、トレーニングの質も、生活の質も上がりました」と彼は満足げに語ります。
まとめ:最高のマットは、最高のトレーニング環境と“安心”をもたらす

今回は、トレーニングの質を左右する「土台」、トレーニングマットの重要性と選び方を徹底的に解説しました。
最後に、最も重要なポイントを振り返りましょう。
- 筋トレには、ヨガマットではなく、専用の「トレーニングマット」が必須
- 選ぶ際は「厚み」「素材」「サイズ」を自分のトレーニングスタイルに合わせて総合的に判断する
- 床の保護や防音は、トレーニングに集中するための最低条件であり、最高の自己投資
- マットは単なる敷物ではなく、あなたの安全と集中力を守り、トレーニングの質を向上させるパートナーである
最高のマットは、あなたから床の傷や騒音への不安を奪い去り、代わりに「安心」と「集中」という、何物にも代えがたい価値を与えてくれます。
さあ、最高の土台を整え、誰にも邪魔されないあなただけの空間で、理想の体をとことん追求しましょう。